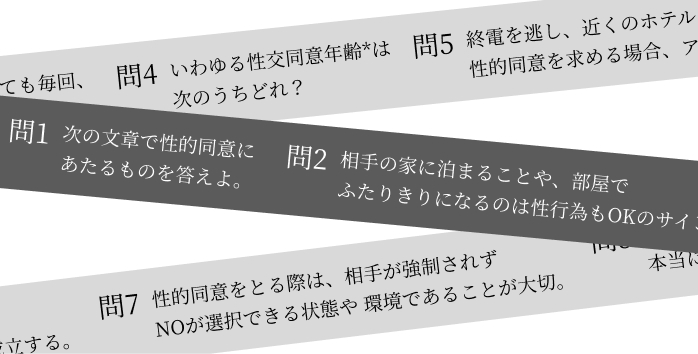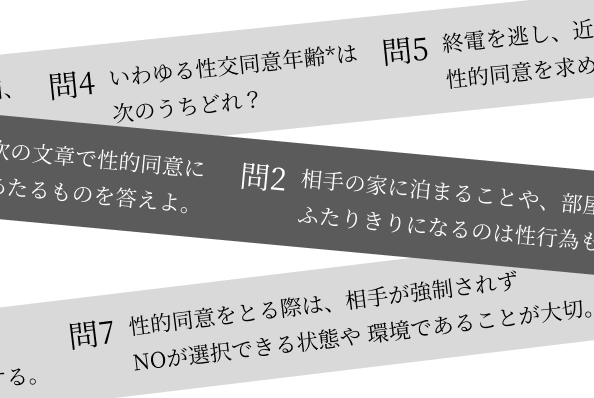SRHRは、私たちが生きていく上でのベースとなるもの〜櫻井彩乃さん
INTERVIEW
(Release)2025年7月30日
若い世代のリアルな声を集め、それらを政策作りにつなげる活動をしている櫻井さん。大切なのは、私たち一人ひとりがSRHRを「自分ごと」にすることだと語ります。
高校2年生の時に言われた言葉に衝撃を受けて

「今の日本ではSRHRに関わる選択肢が限られていることが大きな問題だと思います。たとえ困りごとがあっても、選択肢がないために多くの人が“仕方のないこと”として我慢をしてしまう。それが積み重なり、無理をしてしまっているのが今の社会だと思うんです」
そう語る櫻井彩乃さん。若い世代がジェンダー課題について学び、行動をするサードプレイス「ジェンカレ」などの事業に取り組むGENCOURAGEの代表を務めるほか、政府や自治体の政策にも携わっています。ジェンダー問題に取り組むようになったのは高校2年生の時。同級生に言われた「女は黙って可愛くしてればいい」という言葉に衝撃を受けたことがきっかけでした。
「私自身はそれまで女だからとか男だからとかあまり言われずに育ってきたので、性別による偏見や差別は上の世代のものだと思っていたんです。でも、年代に関係なく、そうした問題があることに気づきました」
以来、さまざまなイベントやNGO、NPOなどの活動に参加しながらジェンダー問題について学び、現在はジェンダー平等の実現を目指して活動しています。2022年に立ち上げた「ジェンカレ」では、30歳未満の若者たちがジェンダーについて学び、アクションを起こすためのプログラムを提供。各分野の第一線で活躍する講師たちによる講義があるほか、それぞれの参加者がジェンダー平等実現に向けてのアクションプランを作り、それを実践するまでのプログラムです。
「参加者の抱える課題には、どれひとつとして同じものはありません。助産師の立場からジェンダー問題を考える人もいれば、演劇とジェンダーをテーマにする人もいます。ゼミ修了生はこれまでに約80名。プログラム終了後も、自治体の政策づくりに関わる人、母校でLGBTQ+教育を行う人など、多くの人が各地でそれぞれのテーマに沿った活動を続けています」
若者たちは声を上げ、連帯し始めている
自分の体に関する選択肢があること、そして一人ひとりがそれを選べる力と知識を持ちながら、安心して人生を歩めること。それが櫻井さんの考えるSRHRです。その実現のためには「意識だけでなく、制度も変えていく必要がある」という信念のもと、若者たちの声を政策に反映するために奮闘してきました。
2020年には第5次男女共同参画基本計画* の策定に向け、〈#男女共同参画ってなんですか〉というプロジェクトを立ち上げ、多くの若い世代の声を提言書としてまとめて政府に提出。その結果、「就活セクハラ防止」「緊急避妊薬の薬局販売検討」などが基本計画に盛り込まれました。また、2020年11月の選択的夫婦別姓の導入を求めたオンライン署名キャンペーン「いつになったら選べますか」では、5日間で3万筆超を集めました。
*…男女共同参画基本法に基づき、国が2000年より策定している男女共同参画社会を実現するための5か年計画。
「2020年の活動を機に、各地域でも若者の声をジェンダー分野の政策に反映していこうとする自治体が増えてきました。また、私が活動を始めた十数年前はユース主体の団体はあまりいなかったのですが、最近は高校生や大学生のグループも増えていて、若者が声を上げて連帯する動きは確実に生まれていると感じています。一方、最近はこうした動きに対する反発や揺り戻しが世界的に起きているのも事実。また日本ではSRHRに関わる制度がなかなか変わらないのも現状です。SRHRの実現は、長い闘いになるかもしれません。だからこそ、こうした動きを一過性のものにせず、しっかり政策などに反映されるよう、声を上げている若い世代を継続的にサポートしていきたいと思っています」
日々聞こえてくる、若者たちの多様な声

こうした活動をはじめ、「ジェンカレ」や全国各地で開いているジェンダー関連の講座を通じ、櫻井さんは日々多くの若者たちの声を直接聞いています。
「高校生からは生理に関する悩みを聞くことがあります。生理が重い時や生理痛が辛い時はどうすればいいのか、情報にアクセスする機会がなかなかないので分からないのです。また、最近首都圏の女子高生から聞いて驚いたのが通学電車での痴漢や盗撮。盗撮用のカメラもますます小型化していて、防ぐことが難しくなってきているらしく、電車に乗るのが怖いと言っていました。
大学生から聞くのは、パートナーとの性的同意や避妊に関する悩みです。さらに年齢が上がってくると選択的夫婦別姓の問題や同性同士で結婚できないこと、子どもを持つか持たないかについての声も聞かれます。また、SRHRの問題というと女性にフォーカスされがちなのですが、男性からの声を聞くことも。たとえばHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、女性は対象年齢であれば無料で接種を受けられますが、男性のワクチン接種に関しては、自治体によっては費用を助成しているものの、全額自己負担のところもあり、受けづらいのが現状です。
地方特有の問題もあります。産婦人科の数が少ない地域だと、困っていることや悩んでいることがあっても気軽に受診できないですし、知り合いがその病院で働いている場合、受診するとプライバシーが筒抜けになってしまうという話も聞きました。
日々たくさんの声を聞いていると、SRHRの課題は本当に多岐にわたっていて、なおかつ日常に密接に関わっていると感じます。そして共通しているのは“選べない”ということ。緊急避妊薬を薬局で買えない、夫婦別姓を選べない、同性婚も認められない——。選択肢があまりにないことが問題の根源にあるのです」
SRHRは「誰かの特別な話」ではない

政府の「男女共同参画推進連携会議」や「子ども未来戦略会議」などの委員を務め、こうした当事者たちの声を国に届けている櫻井さん。SRHRを実現するためには、まず現場の声を聞いて実態を把握し、それを可視化することが重要だと考えています。
「たとえば少子化対策を考える際、まずは生理や避妊に関する悩みを解消したり、性別による生きづらさをなくしたりといった基本的なニーズを満たさなければ、安心して子どもを産める社会には決してならないですよね。実態を十分に理解しないで制度やルール作りを進めても、困っている人を助けることにはなりません。国だけでなく、自治体でも学校でも、どういう困りごとがあるのかをしっかり把握し、それを着実に取り組みに反映させていく必要があると強く思います。そのためには当事者たちの声を聞き続け、それを発信していかなければ。さらには、当事者たち自身がもっと政策決定や制度作りの場に入っていくことも重要だと思います」
一方、もっと小さなことからでも、私たち一人ひとりが今日からできることはたくさんあると櫻井さんはいいます。
「まずは本や映画などを通じ、SRHRの課題や現状について知ることだけでも大きな一歩ですよね。そのうえで、現状を変えたいと思ったら署名やパブリックコメントに参加してもいいし、自分が暮らしている自治体に要望を送ることでも、声を届けることはできます。また、今はそこまで積極的に活動できないという場合、SRHRの実現に向けて活動している人を応援することも大事なアクションです。自分の状況に合わせて、できることをすればいいと思います。そうした個人の小さな積み重ねが、いずれ大きな動きを生み出すのではないでしょうか」
SRHRとは知らない誰かの特別な話ではなく、私たち一人ひとりが生きていく上でのベースとなるもの。そう櫻井さんは力を込めます。
「SRHRを実現することは、誰もが選択肢を持ち、安心して暮らしていける社会を実現すること、そして体や性について安心して声を上げる風土を築くこと。それがひいては教育や労働、経済、政治など、あらゆる分野にいい影響をもたらしてくれると思います。
このキャンペーンを通じて多くの人に『これは自分にも関係しているな』『こんな選択肢もあるんだ』と知ってもらい、SRHRを“自分ごと”にしてもらうことで、一人ひとりの行動が少しずつ変化していけばいいなと思っています。体や生き方の選択肢が広がるということは、その人の人生の可能性が広がるということ。そうした社会をみんなで作っていきたいです」

櫻井彩乃(さくらい・あやの)
1995年生まれ。大学在学中、東京都葛飾区男女平等推進審議会委員などを務める。2020年9月、「#男女共同参画ってなんですか」代表として、内閣府「第5次男女共同参画基本計画」の策定に際し、30歳未満の若者の声を集め、提言書を当時の担当大臣に提出。2022年、GENCOURAGEを設立し、若者がジェンダーについて包括的に学べる「ジェンカレ」を立ち上げる。政府税制調査会特別委員、財政制度等審議会臨時委員、こども家庭審議会臨時委員(基本政策部会/こども・若者参画及び意見反映専門委員会)、奈良県こども・子育て推進アドバイザー(こども・若者の意見聴取担当)などを務める。