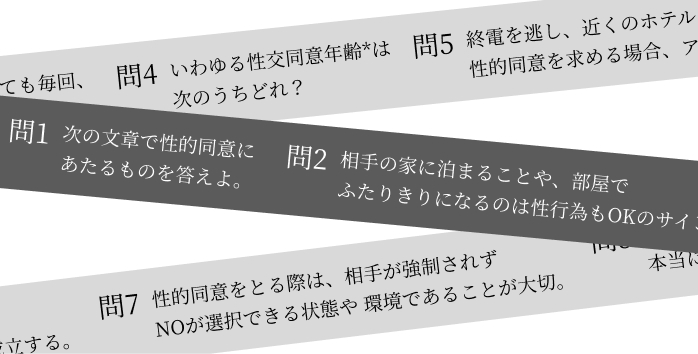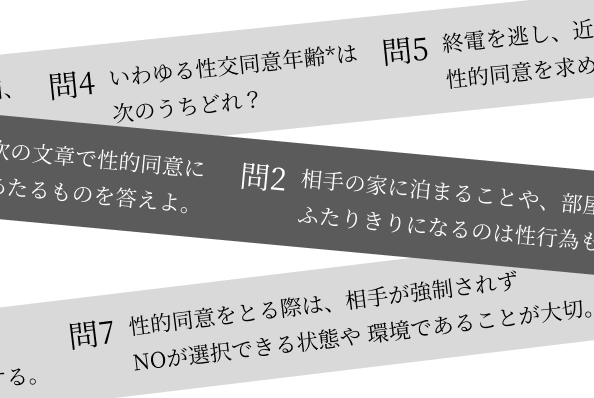「SRHR(性と生殖に関する健康と権利)」は近年になって日本でも広まりつつある考え方ですが、まだピンと来ていない人も多いかもしれません。京都で産婦人科医として働く池田裕美枝さんは、SRHRの普及活動を行う一人です。池田さんに、日本でSRHRの考え方が広がる意義を聞きました。
INTERVIEW
(Release)2025年7月30日
自分らしい生と性を謳歌することができるように

まず、SRHRとは何だろう?というところから教えてください。
池田:日本語訳だと「性と生殖に関する健康と権利」。「THE和訳」という感じなのでスッと入ってこない人もいるかもしれません。
私の今の解釈としては「自分が誰と結婚するかしないか、誰とセックスするかしないか、いつ子どもを産むか産まないか。そういったことをあらゆる人が自分の心と体の声に従って決められるように、社会として応援しよう」という考え方だと思っています。
出産するのは女性なのでSRHRは女性の話だと思われがちかもしれません。
池田:そういうわけではないです。年齢性別にかかわらず、あらゆる人。男性も性的マイノリティも、障害のある人も、高齢者も子どもも、みんな自分の心と体の声をちゃんと聞いて、自分らしい人生なり性なりを謳歌できるように、ということですね。
基本的人権と同じように。
池田:そうですね。「権利」という言葉がつくのは、その人個人の問題ではなくて、社会の問題としてみんなで応援しようという意味を含むからだと思っています。
性や生殖というものが、その人の人生の根幹にかかわってくるという考え方が根底にあると感じます。
池田:誰とセックスするのか、子どもを産むかどうか、いつ産むか。そういうことは、どこに住んでいるか、どんな仕事をしているのかと同じぐらい人生に大きな影響を与えることです。
セクシュアル・アイデンティティについてもそうですが、「調子がいいな」「悪いな」と思うときに、自分の見た目や感覚、またはホルモンバランスなど、性と身体は密接に関係するので、自分とどう付き合うかを考えるときの根底に「性」があると思います。
SRHR、日本での課題は

SRHRについて日本での課題を感じているところはありますか?
池田:大きく2つあって、1つはまず「語らない」ということですね。特に女性が性を肯定的に語ることのハードルが高いように感じます。
男性の場合はセックスを楽しむことはわりと肯定されます。オーガズムがないと射精・生殖できないからかもしれません。女性の場合は、性を楽しむ主体じゃなくてもいいよねという概念が、歴史的にあったのじゃないかと思います。
もちろん、性を楽しむことがすべてではないので全員がそこに重きを置かなくてもいいのですが、語らないために我慢したり悩みを抱えたままにしている人が多いのではないかなと、病院で性の悩みを聞いていて感じます。セックスの悩みについて何十年もふたをして生きてきました、という人がやはりいるので。
もう1つは何でしょう。
池田:身体の自己決定権に関する考え方ですね。
「ボディリーオートノミー」と言いますが、「自己決定」というとイコール「自己責任」に近いニュアンスで捉えられがちです。あなたが決めたのだから、あなたに責任があるよねという。
「自分の体のことは自分で決める」のが体の自己決定権ですが、それだけではない?
池田:例としてよく挙がるのが児童婚です。発展途上国で貧しい村から10代の女の子がお金持ちの家に嫁ぐということがありますよね。「あなたの親や兄弟がこれで明日からごはんを食べていけるよ」と言われたら、その子はもしかしたら喜んで「結婚する」と言うかもしれません。
けれど結婚相手のおじさんとセックスするのが怖かったり、体にワクワクした反応が起こりにくいのであれば、それは体の自己決定権を尊重していないと表現されるんです。
頭で計算して出した「決定」だけではない。
池田:頭だけで決めるのではなく、もうちょっと心と体に寄り添って、その反応を尊重する。そういう考え方なんですよね。
日本の私たちの社会って、「個」よりも、人との関係性を重んじるところがありますね。人と対峙した際にその人との間に立ち現れる「私」の概念があって、自分らしさよりも、あなたに期待される自分でいようとするところがありますよね。わかりやすく言うと、輪を乱さない雰囲気。良い悪いではなくそういう文化だと思います。
確かにそうですね。
池田:そういう文化の日本に、ボディーオートノミーを無理に押しつけても浸透しないかもしれません。
少し話は変わりますけど、私が医師になった2000年代前半はまだ、末期がんの患者さんに家族の意向で告知をしないということがまだあったんですよ。
「死」についても「性」についても語りたがらない。語らないで「察してください」という、「察し」を求める傾向があるのだと思います。自己決定権が大事と言っても、周囲との兼ね合いを考えながら察する文化で80年間生きてきた人が、急に人生の終盤で「終末期についてあなたのご意見は」と言われても困ってしまう。
そんな日本社会にも変化はあると思いますか?
池田:SRHR尊重の方向へ行くのではないかなと私は今は考えていて、もっと性について語ることができないかと試行錯誤しています。
相手の意向に押し切られてセックスに流れるよりも、自分の性の感覚に自覚的になれるといいですよね。
個人主義と「察する文化」のバランスを

日本国内でSRHRを推進することで、どのような変化があると思いますか?
池田:バランス感覚が良くなるということだと思うんですよ。
全体主義の最たるものが第二次世界大戦で、個人の尊厳よりも全体の利益を尊重しましょうとなって、その反省から今の日本社会がありますが、その法律や制度が輸入されたものだから噛み砕けていない部分がある。個人主義が噛み砕けていない部分があるのではないかと思います。
SRHRがもっと語られるようになると、全体の利益や関係性の中での自分のあり方を考えていく部分と、自分の心と体の声を大切にすることのバランスが良くなっていくのではないかと思います。
なるほど。
池田:日本は今すごく少子高齢化が進んでいて、これはもう避けられない状況です。いま、生殖年齢にある人口が減少しているので、たとえ出生率が2まで上がっても、もう人口は増えないです。こういった人口減少社会では、経済不安から人の意識は個人主義から全体主義に移行しがちなのですが、政策研究者のデータによると、人口減少社会こそ、全体主義より個々の独自性が伸びる個人主義であるほうが、経済や社会が発展するそうです。(人口減少社会のデザイン:広井良典)
戦後の日本の経済発展は人口ボーナスを最大限に活かして同じ価値観のもとに競争していたというところがありますが、社会構造が変わっていく中で、これからは全体主義より個人主義。自分らしさを活かしあい、共通資産をシェアして支え合う社会のほうが、発展しやすいのでは、と思います。
最後の質問です。SRHRの重要性を多くの人が理解し、より良い社会になるために必要なことは何だと思いますか?
池田:日本では「性教育」という言葉に拒否感がある人が多いから、その拒否感を減らしていきましょう……ということよりも、価値観の多様性やコミュニケーションの勉強、自分との付き合い方の勉強、その機会が増えることの方がよっぽど大切だと思っています。
そのためにできることをオールセクションで、あの手この手でやっていかなくちゃいけない。
子どもや女性のことを「面倒を見てあげるもの」「保護してあげるもの」と扱うのではなく、それぞれが主体性を育んでいく存在だと理解する。その概念を浸透させることにSRHRの普及はつながっていくと考えています。

池田 裕美枝(いけだ ゆみえ)
医療法人心鹿会 海と空クリニック京都駅前院長/一般社団法人SRHRJapan代表理事/NPO法人助成医療ネットワーク理事長 京都大学医学部卒業。内科医として研修を受けた後、「女性のヘルスケアの専門家になりたい」と考えたことから産婦人科に転向。さらに深く学ぶため、2011年にイギリスで、リプロダクティブ・ヘルスディプロマを修了。2013年にはアメリカで女性内科の研修を受ける。 社会的困難女性を支援する人のための ソーシャルワーク・プラットフォーム「KYOTO SCOPE」の運営やユースクリニック開業など、京都と国内外を行ったり来たりしながらSRHRに携わる活動を続けている。