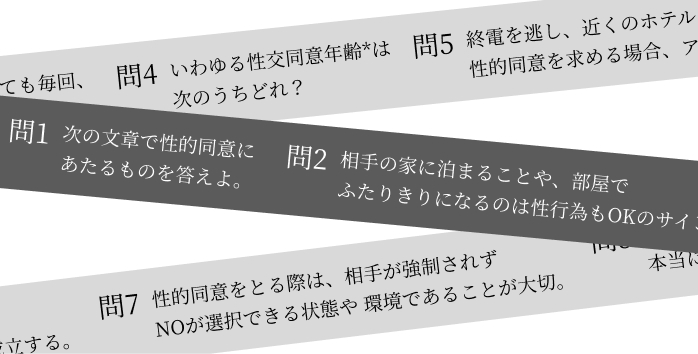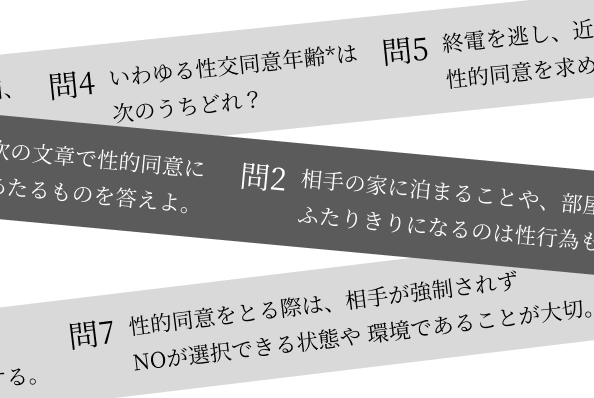カンボジア、台湾、韓国の状況を知る〜「アジア議員会議」 参加者インタビュー
INTERVIEW
(Release)2025年10月31日
2025年10月7日に開催された「生命(いのち)の安全教育:尊厳を守る教育に関するアジア議員会議」において、台湾、韓国、カンボジアから参加した3名に、それぞれの国における性教育の状況について聞きました。
■カンボジアの性教育、HIVの脅威が原点「生きるため」の学びに:Yos Phanita 氏
.jpg)
カンボジアの性教育は、差し迫った「命の脅威」への対策から始まりました。1990年代初頭、内戦終結と平和構築の過程でHIV感染とエイズの発症が深刻な社会問題となりました。上院議員で、医師としての経験も持つYos Phanita氏に、その歩みと現状、そして課題について話を聞きました。
「カンボジアの性教育は、歴史的な背景から始まりました」とPhanita氏は語ります。カンボジアは、ポル・ポト政権時代を含む長い戦争と内戦を経て、社会の再建をゼロから進めなければなりませんでした。1990年代に入り、日本などの支援を受けながらようやく平和への交渉が進む中、新たな脅威が社会を襲いました。
「1991年頃、HIVとエイズはカンボジアで深刻な病気となり、社会はパニック状態になりました。HIVがどのように感染するかを考えたとき、『性』に関する教育は、贅沢品ではなく、生きるために『必要不可欠』なものとなったのです」
制度化への転機
当時はまだ性教育の正式なカリキュラムがなく、地域の教師や医療従事者が自主的に啓発活動を行っていたといいます。大きな転機となったのは2000年代初頭です。法整備とともに教育制度に性教育が徐々に組み込まれ、2019年には政府による「国家ガイドライン」が策定されました。これに基づき、2021年から2030年までの国家行動計画が進められています。
「現在は小学5年生から高校3年生まで、保健教育の一環として性と生殖に関する内容を学びます」とPhanita氏は説明します。特徴的なのは、これが教育省だけでなく、保健省や財務省なども関わる“省庁間行動計画”として進められている点です。
「性教育は独立した科目ではありません」。教科書を見せてもらうと、性教育は「6つの柱」の一つとして位置づけられていました。具体的には、応急処置、メンタルヘルス、栄養、衛生、環境衛生などと並び、「性と生殖に関する健康」として包括的に教えられています。
伝統的価値観との「バランス」
とはいえ、「カンボジアには、他のアジアの国々と同じように、性について公の場で語ることをためらう保守的な雰囲気もある」とPhanita氏は言います。
「社会は固定されたものではなく、常に変化しています」と指摘します。「新しい考えを導入しすぎるのは良くありませんが、全く変わらないのも正しくありません。『バランス(均衡)』が重要です」。政治家には、社会の変化を見極め、「ちょうど良い量、タイミング、スピード」で改革を進める責任があると語りました。
資金不足と人材育成が課題
一方で課題も明確です。最大の問題は「資金不足」です。「生徒に教える前に、まず教師を訓練しなければなりません。正しい知識と伝え方が重要です」とPhanita氏は人材育成の必要性を強調します。国家レベルでの教師養成は進んでいるものの、実際に授業が行われる“地区レベル”での研修がまだ十分ではないといいます。
インタビューの最後にPhanita氏は、資金や人材育成といった課題に加え、それらすべての前提となる「真の課題(The real challenge)」として「平和と安定」を挙げました。「私たちは経済成長を推し進め、教育や医療制度を再構築したいです。しかし、平和と安定がなければ、そのすべてを達成することはできません」と強調しました。
■台湾 アジア初の同性婚を実現、その先へ:台湾ジェンダー平等教育協会(TGEEA)Hang Yichen氏
.jpg)
アジア初の同性婚を実現した台湾。だが「ジェンダー平等教育」は今、岐路に立たされています。「台湾ジェンダー平等教育協会(TGEEA)」のHang Yichen事務総長に「まだ克服していない」というバックラッシュの現状と、法律と現場のギャップ、台湾の次なる挑戦を聞きました。
悲劇を「法」へと変えた歴史
台湾におけるジェンダー平等の法整備は、複数の痛ましい事件をきっかけに進められてきました。最初の転機は1996年の彭婉如(ポン・ワンルー)事件。女性政治家であり人権活動家でもあった彭氏が殺害された事件を機に、「女性の権利」を守る法整備が進みました。
その4年後の2000年、もうひとつの事件が台湾社会を揺るがします。高校生の葉永鋕(イェ・ヨンジー)さんが、女性的な性表現を理由にいじめを受け、学校のトイレで命を落としました 。この彼の死は社会に衝撃を与え、「性別や性的指向、性表現にかかわらず、誰もが安心して学べる環境を」と訴える声が高まりました。
この流れが、2004年の「ジェンダー平等教育法」制定につながります。
教育が育てた同性婚、だが「まだ道半ば」
法律はできたものの、当初、教育現場は戸惑いました。Hangさんによれば、教師たちにとって「ジェンダー平等」は新しい概念で、「どう教えればいいのか分からず、教材もなかった」と言います。TGEEAのようなNGOが、海外から学びながら教材開発を支えました。
ところが2011年、反LGBTQ+団体が組織され、学校での教育に強く反発する「バックラッシュ(反動)」が起こります。彼らは、ジェンダー教育が次世代をより包括的にすることに気づき、抵抗を強めました。
それでも2019年、台湾は同性婚を法制化します。Hangさんは、その最大の要因を「教育の世代効果」だと分析します。「若い世代は、ジェンダー平等教育法のもとで学び、LGBTQ+の人々についてよく知っています。私たちの周りには多くのLGBTQ+の友人がいて、これは“遠い誰か”の話ではなく、自分たちに近い人の問題なのです。だから若い世代は、上の世代よりずっと協力的でした」
同時に、Hangさんは台湾の特殊な国際事情も指摘します。「台湾政府は、『人権をしっかり守っている国だ』と国際社会に示す必要があります。それは、『中国とは違う』という価値観を示す上でも重要でした」
しかし、Hangさんは「私たちはバックラッシュをまだ本当に克服したわけではありません」と強調します。同性婚は実現しましたが、トランスジェンダーの権利など、今も激しい議論が続く課題は山積みです。
現在の大きな壁:「法」と「教室」のギャップ
制度は整ったものの、課題は山積みです。第一の壁は「バックラッシュ」。反ジェンダー運動は、国際的な資金を得て組織化され、政治的な影響力も増しています。
第二の壁は「現場」。教師の研修不足や、教科書の「時代遅れ」が深刻です。Hangさんは「HIV教育では、今も間違った記述が残っています」と指摘。包括的性教育(CSE)も、教育省がマニュアルに紹介しただけです。Hangさんによれば「教師たちは普段マニュアルを読みません 」。現場に届いていないのが実態です。
次の挑戦と日本への期待
TGEEAは2029年のカリキュラム改訂でCSEを正式に組み込むことを目指しています。最後にHangさんは日本へ期待を込め、こう語りました。「日本には、ぜひ同性婚を早期に法制化してほしいです。支持率は台湾より高いと聞いています。それなのに、なぜまだ実現していないのか不思議です」
■韓国の性教育、先行法制化の光と影:性文化研究所Lala共同代表 Lee Su-ji氏
.jpg)
韓国から登壇した「性文化研究所Lala」共同代表のLee Su-jiさんは、韓国における性教育の先進的な側面と、その裏にある複雑な実情を明らかにしました。東アジアでいち早く性教育を「法制化」した韓国ですが、なぜそれが可能だったのでしょうか。また背景には何があったのでしょうか。Leeさんに話を聞きました。
先行した法制化の実態
韓国では2001年に、すべての小・中・高校で年間10時間(2013年以降は性暴力予防教育3時間を含む15時間)の性教育が義務化されました。東アジアの中では比較的早い導入で、非常に先進的に見えます。 しかし、Leeさんはこうした評価にやや否定的な見方を示します。
「2001年に導入された当時、実際の中身は性教育と呼べる内容ではありませんでした」。当時は独立した科目ではなく、社会科や家庭科などに分散され、学校現場での実施状況には大きな差があったそうです。初期の教育内容は「避妊や生殖ではなく、出産に重きを置いたものでした。同性愛は認められず、結婚の神聖さや純潔を説く道徳的な側面が強かった」と言います。
法制化の背景と市民社会
それでも、なぜ韓国は早い段階で法制化に踏み切れたのでしょうか。
Leeさんはまず、1994年の国際人口開発会議(カイロ)や1995年の世界女性会議(北京)など、国際社会からの「青少年への性教育の必要性」という勧告を挙げました。しかしそれ以上に大きかったのが、90年代後半に深刻化した性暴力や援助交際といった社会問題だったと指摘します。 「90年代後半、韓国で性暴力や援助交際がクローズアップされました。それを受け、教育界から『性教育の不在が背景にある』との声が上がり、法制化の機運が高まりました」
ただ当時は「性売買や性暴力を防げばいい」という、対症療法的な「1回限りの教育」という流れでした。 これに「待った」をかけたのが、女性団体をはじめとする市民社会でした。「『1回きりではなく、具体的かつ継続的に性教育を行うべきだ』という強い要求が、法制化に結実した」と言います。
原動力は「民主化」
法制化を後押しした市民社会の力について、Leeさんは80年代後半の「民主化運動」が源流だと見ます。 「政治の民主化が、社会や家庭、学校の民主化議論につながりました。例えば『家庭内暴力は民主主義の否定ではないか』という議論が女性団体から起こりました。女性の体への統制や抑圧も民主主義の否定だ、という主張でした」
「民主主義の実現」という大きな文脈の中で、性暴力や人権の問題が位置づけられました。この流れが、1998年の大統領直属「女性特別委員会」(後の女性家族部)の設置、そして2001年の法制化へとつながりました。
現場の混乱と問題ある指針
こうして「理念先行」で始まった性教育ですが、教育現場は大きな混乱に陥ります。保健教員らから「『指導案がなく、どう教えていいか分からない』」との声が上がりました。 この声に押され、2015年に教育部(日本の文科省に相当)が全国統一の性教育ガイドラインを作成しました。 しかし、これが新たな火種となります。内容に「性平等」や「性的マイノリティ」といった言葉が含まれていたため、保守的な層から「同性愛を助長する」と激しい反発が起きたのです。結果、全面改定されたガイドラインは、逆に「性差別を助長するような内容」になってしまったとLeeさんは厳しく批判します。 「(改定版には)『男性はヌードに弱く、女性はムードに弱い』とか『同性のセックスはダメ』『結婚後にすべき』など、ひどい内容が書かれていました』」
「空白」が生んだ自由
2023年、この問題あるガイドラインは法改正に伴い、正式に廃止されました。新たな指針は未策定で、現在は国の指針が「空白」という異例の状態です。 しかし、Leeさんはこれを「不幸中の幸い」と表現します。
「ガイドライン廃止で縛るものがなくなり、ご自由にどうぞ、というのが今の状況です」。 ソウル市や京畿道など主要自治体は、独自の包括的性教育ガイドラインを整備しました。LalaのようなNPO(非営利団体)は、国の介入なく、ソウル市などの先進的な「包括的性教育(CSE)ガイドライン」に沿って活動できるようになったのです。
新たな課題と教育の役割
一方で、課題は山積みです。Leeさんが今、最も危機感を抱くのは「デジタル性犯罪」と「10代、20代男性の極右化」であり、それが弱者への「嫌悪感(ミソジニー)」を増幅させていることです。 Leeさんは、安全な関係性の築き方や感情表現を学ぶ包括的性教育こそが、社会に広がる「嫌悪」や「分断」を乗り越える鍵になると信じています。