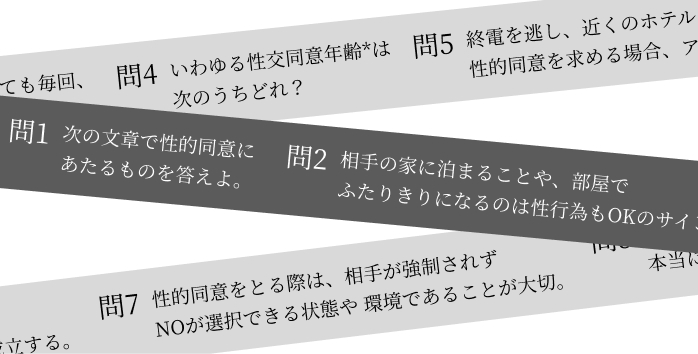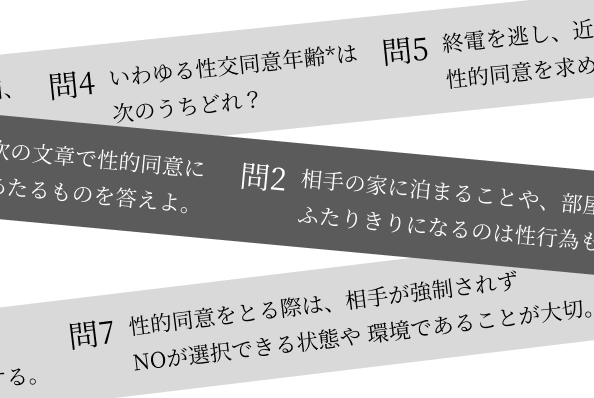【開催報告】「生命(いのち)の安全教育:尊厳を守る教育に関するアジア議員会議」
EVENT
(Release)2025年10月30日
2025年10月7日、衆議院第一議員会館において「生命(いのち)の安全教育:尊厳を守る教育に関するアジア議員会議」が開催されました。本会議は、アジア人口・開発協会(APDA)が主催し、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンが共催、国際人口問題議員懇談会(JPFP)生命の安全教育プロジェクトチームおよび国際家族計画連盟(IPPF)が協力しました。アジア各国の国会議員、専門家、行政関係者、市民社会代表が一堂に会し、人間の尊厳を守る教育の在り方を多角的に議論しました。
開会・基調講演
.jpg)
まず、堀内詔子JPFP PT座長代行の進行のもと、主催者を代表して武見敬三APDA理事長が挨拶を行いました。続いて、上川陽子JPFP会長・AFPPD議長・前外務大臣が基調講演を行い、「生命の安全教育」を通じた人権尊重および加害・被害防止の重要性を強調しました。性教育が社会的に敬遠されがちな中で、より受け入れやすい概念として「生命の安全教育」を提唱し、国際的な法整備と議員間連携の推進を訴えました。
また、上川氏が会長を務める国際人口問題議員懇談会(JPFP)では、専門家や市民社会と連携して生命の安全教育を推進するプロジェクトチーム(PT)を設置し、アジア太平洋30カ国をつなぐ人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)議長として、国際的な政策協力を主導していることを紹介。子どもの安全を守ることは社会全体の責務であると述べ、各国の経験共有と人権・教育支援の枠組み強化に向けた決意を表明しました。
セッション1:日本の現状と課題
.jpg)
第1セッションでは、日本における「生命の安全教育」の現状と課題が、医療・行政・立法の三側面から議論されました。 議長は寺田静参議院議員・JPFP幹事が務めました。
丸の内の森レディースクリニック理事長の宋美玄氏は、日本のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(SRHR)の現状を報告し、避妊・中絶・性教育の各分野での制度的遅れを指摘しました。避妊手段は依然としてコンドームが主流で、経口避妊薬や緊急避妊薬は保険適用外で高額な自己負担を強いられています。中絶には刑法上の堕胎罪や配偶者同意の要件が残り、女性の自己決定権を制約していると述べました。これらの制度的不備が、時に新生児遺棄などの悲劇を招く現実を示し、根底には性教育の欠如があると指摘しました。宋氏は、性教育を「人権教育」として再構築し、すべての人が自らの身体と選択を尊重できる社会基盤を整える必要があると訴えました。
続いて、宮路拓馬外務副大臣が、政治の場で男性議員として、性と生殖に関する課題を語ることが可能になりつつある社会的変化について触れ、女性の健康課題や性犯罪被害防止が少子化対策の根幹に関わることを指摘し、すべての子どもに等しい教育機会を保障する環境整備の重要性を強調しました。
討議のまとめで寺田議長は、妊娠・中絶・出産がいまだに「女性の自己責任」とされる社会構造を改め、特に、中絶における配偶者同意の要件などが女性の選択を制約している現状を踏まえ、法改正の重要性を訴えました。「No Means No」から「Yes Means Yes」への文化的転換には、法律と社会意識変革の両輪が不可欠であると述べ、若年層が安心して支援を受けられるユースクリニック整備や、年齢や保護者の同意に左右されないアクセス体制の整備が必要であり、さらに、医療・薬局の地域連携など、政治による公的支援体制の拡充を提案しました。
セッション2:各国事例報告①:東・東南アジアにおける教育アプローチ
本セッションでは、日本および東・東南アジア地域の教育現場における「生命の安全教育」の実践例が紹介されました。
文部科学省の中園和貴課長は、日本での生命の安全教育の導入経緯を報告しました。2017年の刑法改正を契機に、性暴力防止を目的とした教育強化が進み、「子どもを加害者・被害者・傍観者にさせない教育」として国会議員連盟の提言を踏まえ教材が整備されました。教育理念は「生命の尊重」「他者理解」「距離と境界の認識」を柱とし、2022年には生徒指導提要に正式に位置づけられました。教材は文科省ウェブサイトで公開され、学校現場で自由に活用できる形で提供されています。

続いて、韓国LALA性文化研究所共同代表のLee Su-ji氏が登壇。韓国では2001年より学校での性教育が義務化され、現在は年間15時間実施されていますが、内容や実施状況にはばらつきがあると指摘しました。研究所では、①身体理解と衛生教育、②同意と境界の学習、③デジタル性暴力防止教育の三本柱で独自プログラムを展開。絵本やゲームを用いた体験型学習を通じ、障害児を含む全ての子どもが他者尊重と自尊感情を学べるよう取り組んでいると述べました。
セッション3:各国事例報告②:立法・政策事例
本セッションでは、東・東南アジア諸国における包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education: CSE)の推進とデジタル犯罪の課題について、立法および政策の視点から各国の取り組みが報告されました。
フィリピン上院議員立法担当首席官のJaye Bekema 弁護士は、2012年に制定された「責任ある親子関係およびリプロダクティブ・ヘルス法(RH法)」に基づく制度的枠組みを紹介し、CSEが教育課程に正式に位置づけられている現状を説明しました。同意や相互尊重の概念が教育内容に反映されつつある一方、若年妊娠やオンライン搾取が依然として深刻な課題であると指摘し、文化的背景に即した教育手法の重要性を強調しました。
牧島かれん衆議院議員・JPFP副会長は、日本における子どもへの性暴力およびデジタル犯罪の深刻化を報告しました。 警察による性犯罪検挙件数は過去10年で最多を記録し、SNSを介した被害、児童ポルノ、グルーミングなどが拡大していると指摘。これに対し、撮影罪の新設や性犯罪歴確認制度(いわゆる「日本版DBS」)の導入など、被害防止に向けた法整備の進展を紹介しました。また、こども家庭庁によるインターネット利用の安全対策、さらにディープフェイクや違法コンテンツへの国際的な取り締まりの必要性を述べ、テクノロジーと国際協力の両面から子どもの安全を守る取り組みを推進する姿勢を示しました。
インドネシアのSri Wulan Sutomo議員は、自国の現状として、「ARH(思春期生殖健康教育)」の導入とその課題を報告しました。ARHは性感染症予防、児童婚防止、ジェンダーに基づく暴力防止を柱とし、インドネシアの文化的・宗教的価値観に適合した形で展開されています。10〜24歳の若年人口が7,000万人を超える中、15〜19歳の出生率は1997年の1,000人当たり59から2023年には26.4へと半減したものの、児童婚や若年層への暴力は依然として深刻であると指摘しました。課題として、全国統一カリキュラムの欠如、宗教・文化的タブーによる内容の制約、教員研修の不足、家庭や地域社会の理解不足、誤情報の拡散などを挙げ、持続的な教育体制構築の必要性を強調しました。
セッション4:次なるステップ 制度設計と社会理解の促進戦略と国際的連携
本セッションでは、若者の安全と権利を守るための制度的枠組み、社会的理解の促進、そして国際的な連携の方向性について、多角的な議論が行われました。
ニュージーランド国会議員のキCatherine Wedd議員は、若年層、特に少女たちを有害なSNS依存や有害コンテンツから保護する法制度の重要性を訴えました。同議員は、現在ニュージーランド議会で審議中の「16歳未満のSNS利用を禁止する法案」を紹介し、その背景にある社会的課題を説明しました。フランス、英国、ノルウェーなど諸外国における同様の立法動向にも言及し、保護者・教育関係者・政治が一体となって未成年者の安全を守る包括的な法制度の構築が急務であると強調しました。

続いて、在日オーストラリア大使館Stuart Watts政務担当公使が登壇し、外交政策および国際協力の観点からデジタルおよびメディアリテラシー教育が果たす役割を論じました。Watts公使は、オーストラリア政府が国際開発援助(ODA)の枠組みで推進している教育支援プログラムを紹介し、教育へのアクセス拡大、女性の政治参画促進、暴力防止に関する啓発活動を重点分野として位置づけていることを説明しました。さらに、アジア太平洋地域におけるパートナーシップの強化を呼びかけ、各国の議会・政府・市民社会が協働して「安全で包摂的な学びの環境」を整備する必要性を訴えました。最後に、公使は外交の立場から、教育支援および人間の安全保障の推進に対するオーストラリアの継続的なコミットメントを示しました。
セッション後半では、議長を務めた牧原秀樹前法務大臣・JPFP幹事長の進行のもと、Watts公使に対し各国代表から活発な質疑が行われました。
Yos Phanita 議員 (カンボジア)は、オーストラリアの発表にあった「思春期の子どもに対する猶予期間」の概念に着目し、文化的背景によってこの期間が異なるのではないかと指摘しました。また、SNSや動画配信プラットフォームを運営するグローバルテクノロジー企業の社会的責任についても質問し、「有害な影響を及ぼす企業活動に対し、国際的な枠組みの中で金銭的・制度的な貢献を求めるべきではないか」と提案しました。これに対しWatts公使は、「オーストラリアでは国内研究の結果を踏まえ3年間の猶予期間を設けているが、文化的・人口的条件が異なる国々では異なる基準が自然である」と回答。企業責任についても「グローバル企業の影響力は極めて大きく、責任ある行動を促す国際的な枠組みづくりが必要である」と述べ、Phanita議員の見解に同意を示しました。
さらに、池上清子 APDA 副理事長・常務理事/プラン・インターナショナル・ジャパン理事長からは、オーストラリアがSNSの利用年齢を「16歳未満禁止」としている点に関する質問があり、その基準設定の根拠と国際的適用可能性について尋ねました。これに対しWatts公使は、「16歳という年齢は、13〜16歳未満の層でSNS依存や心理的影響が最も顕著に見られるという国内外の研究結果に基づくものである」と説明。そのうえで、「この基準を他国に一律に当てはめることは想定しておらず、各国が自国の社会的・文化的文脈に基づいて独自に判断すべきである」と述べました。
本セッションを通じ、デジタル時代における子どもの権利保護、教育制度の再設計、そして各国間の政策協調の必要性が改めて確認され、今後の国際的な協働の方向性が示されました。
閉会式
阿部俊子文部科学大臣・PT座長は、各国の事例共有に謝意を表し、共通課題に加え応用可能な優良実践が多数示されたと総括。「生命の安全教育を含む教育政策の制度化」「法整備と実践の連携」「社会理解の促進」を今後の方向性として掲げ、国際ネットワークの中での協調を呼びかけました。「本日の対話を次の行動へつなげることが我々の責務である」と述べ、閉会の辞としました。
.jpg)
文責:APDA